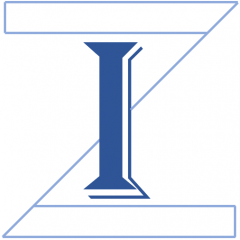The Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards CHEERS statement CHEERS声明ー医療経済評価における報告様式のガイダンスー は2013年に International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes (ISPOR) 国際医薬経済・アウトカム研究学会から発表された医療経済評価に関する論文の執筆ガイダンスである。Husereau D, Drummond M, Petrou S, Carswell C, Moher D, Greenberg D, Augustovski F, Briggs AH, Mauskopf J, Loder E, ISPOR Health Economic Evaluation Publication Guidelines-CHEERS Good Reporting Practices Task Force: Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards (CHEERS)–explanation and elaboration: a report of the ISPOR Health Economic Evaluation Publication Guidelines Good Reporting Practices Task Force. Value Health 2013;16:231-50. PMID: 23538175。白岩らの日本語訳も発表されている。
以下の項目について、望ましい執筆方法が解説されている:
タイトルと抄録:タイトル、抄録、序論:背景と目的、方法:対象集団とサブグループ、状況や場所、研究の立場、比較対照、分析期間、割引率、アウトカムの選択、効果の測定、選好に基づくアウトカムの測定や評価、資源消費と費用の推計、通貨・時点・換算、モデルの選択、仮定、解析方法、結果:研究で用いたパラメータ、増分費用と増分アウトカム、不確実性、異質性、考察:研究結果・限界・一般化可能性・現在の知見、その他:資金源、利益相反
太字で示した項目は、医療経済的解析のデータソースとして用いられる臨床研究の臨床疫学的な視点での評価に関係する。