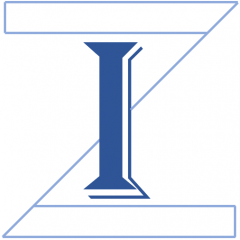Guidelines and Economists Network International ( GENI )という国際的組織があります。そのAgenda課題は、
” To facilitate the effective integration of Clinical Practice Guidelines (CPGs), economic and clinical evidence into national decision making and clinical practice in the health sector, especially hospitals and primary care. “
すなわち「 診療ガイドライン、経済的および臨床的エビデンスを特に病院とプライマリケアの健康セクターでの医療と国レベルの意思決定のために効率的に統合することを促進すること 」です。ここではEconomic evidenceとClinical evidenceという言葉が使われています。
GENIの Chair: Michael Drummond (UK) CEO: Kathryn M. Antioch (Australia) とBoard Members: Louis Niessen (USA) 、 Hindrik Vondeling (Denmark) らの論文が2017年に発表されており、”Economic evidence”を”Clinical Practice Guideline”と”National decision making”にどのように取り入れるかについて、オーストラリアでの体験を踏まえて、述べています。
こちらの論文です。 Antioch KM, Drummond MF, Niessen LW, Vondeling H: International lessons in new methods for grading and integrating cost effectiveness evidence into clinical practice guidelines. Cost Eff Resour Alloc 2017;15:1 DOI 10.1186/s12962-017-0063-x. PMID: 28203120
Economic evidenceはCost-effectiveness analysis (CEA) thresholds, Opportunity cost, Willingness-to-pay (WTP)に関するものです。ただし、End-of-life therapiesは特別の考慮が必要とされます。さらに、”Involvement time, logistics, innovation price, price sensitivity, substitutes and complements, absenteeism and presentismに関わってきます。
Economic evidenceのグレーディングにはThe Consolidated Guidelines for the Reporting of Economic Evaluations (CHEERS) 24 item check listとthe Drummond ten-point check listおよび結果をスコア化するための質問票を用いることを提案しています。(CHEERSとその日本語訳については別の投稿で紹介しました)
この論文のTable 1 Assessing CEA evidence using shadow prices in Australia: NHMRC*ではRanking of evidence on costsとRanking of evidence on effectsの組み合わせで、生存年あたりの費用($)によって推奨する/推奨しないという判定の基準が示されています。(*National Health and Medical Research Council)
そして、”Priority setting remains essential and trade-off decisions between policy criteria can be based on MCDA, both in evidence based clinical medicine and in health planning.” すなわち、「優先度の設定は必須であり、方針基準の間のトレードオフのある意思決定はMCDA(Multi-Criteria Decision Analysis)をよりどころにできるであろう」と述べています。MCDAについてはISPORのGood Practice Guidelines for conduction MCDAの論文、Thokala P 2016とMarsh K 2016が引用されています。(以前の投稿で紹介しました。)
Willingness to pay per QALYまたはLYG (life years gained)の受け入れ可能な最大値(閾値)を設定することで、Cost-Effectiveness Analysis (CEA)のDecision ruleを設定できるのではないかと述べられています。その最大値は、患者と家族のQOL, 生存の改善、機能的状態、重篤でまれで予防可能であるいは若年で永続的な効果につながるか、他の選択肢がない、その介入が平等の見地から他のセクションへの有害な流れを防止できる、などの項目を検討したうえで、妥当性が検討されます。
診療ガイドライン作成者は最新のCost-effective methodologyを知る必要があり、NICEのReference Caseはその一つであることが述べられています。NICEの医療経済評価については以前の投稿で紹介しました。
また、International Health Economists Association (iHWA )という組織があり、2019年7月13-17日スイスBaselで学会が開催されます。そのミッションは以下のとおりです。医療経済学の発展が大きな目的のようです。
“iHEA’s mission is to: Increase communication among health economists; Foster a higher standard of debate in the application of economics to health and health care systems; and Assist young researchers at the start of their careers. “
さて、MCDAについてですが、医療経済学的な評価の結果と臨床的な効果の評価は異なる尺度が用いられているので、MCDAでトレードオフのある複数の評価項目に含めて評価し介入を比較するのはワンステップではできません。やはりスコア化のステップが必要です。